☆ 当ブログは、プロモーションを含みます。
ロリポップ!今日のニュースで、「SFTSに感染した猫を治療していた獣医師が、感染し亡くなった疑いがある」というニュースを見ました。
これは他人事ではないと感じ、改めて情報共有したいと思います。
- 「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」
- SFTSウィルスを保有するマダニに咬まれる事により感染
- 症状:発熱、消化器症状(嘔吐、下痢、腹痛、下血)が主で、腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ筋腫脹、出血症状など
今回のニュースでは「SFTSウィルスを保有するマダニ → 猫 → 獣医」がルートでしたが、これがもし自分の愛犬だったとしたら、自分や家族にも影響が出る可能性があるのです。
マダニの投薬は愛犬家にとって今では当たり前となっており、私が新人トリマーだった頃(20年以上前ですが)から比べると、マダニが付いているわんちゃんはかなり減ってきました。
それでも、お住まいの地域や散歩させる場所により、ハプニング的に付いてしまう事があります。
マダニはどこに潜んでいるの?
今回問題になったマダニですが、山の中の話と思っていませんか?
” 自分は都会に住んでいるから大丈夫 ” そう考える人もいるかもしれません。
実は、マダニの生息域は意外と身近にあるのです。
- 公園などの草むら
- 土手などの草むら
- ドッグランなどの草むら 等
「うちの子は、草むらに顔を突っ込みたがるのよ~」
「うちの子は、草むらに顔を突っ込みたがるのよ~」
このセリフ、本当によく聞きます。
もちろん我が家の愛犬も草むらが大好き。
草むらには色々な匂いがありますからね、気になって匂いを嗅ぎたい気持ちを抑えられないのは当然でしょう。
でも、マダニの活動が活発になる温かい時期は、心を鬼にして、阻止した方が良いと思います。
なぜなら、犬の体はマダニにとって、家であり、食料でもあるからです。
マダニの立場になって考えてみると、草むらにいたら、向こうから食料がたっぷり詰まった家が歩いてやってくるのです。
鴨がネギと家を背負ってやってきたら、そりゃあ、飛びつくでしょう。
「嗅ぎたい気持ちを阻止するなんて、可哀想!」
「嗅ぎたい気持ちを阻止するなんて、可哀想!」
「そんなに神経質にならなくても…」
色々な意見があると思います。
では、マダニ対策をもう一度見直してみましょう。
- マダニの投薬
- 散歩後のブラッシング
- こまめなシャンプー(皮膚checkの為)
「散歩後のブラッシング」は大切!
SFTSウィルスを保有していないダニに咬まれたといても、痒みやアレルギー症状が出る場合もあるので、春~秋にかけては特に十分な「散歩後のブラッシング」を心がけたいところです。
マダニは一年中いますが、冬間は活動が鈍るので見かける事は少なくなります。
春になり気温が上がると一気に活動的になってきますので、注意が必要です。
犬は、草むらに顔をつっこんで匂いを嗅ぎたがりますが、犬の行きたい方に行かせてたらダニがついた!という事例はいくつもあります。
草むらが大好きな子には、しっかり投薬をしてから散歩に行きましょう。
散歩で愛犬が連れて帰ってきたマダニが床を這って、そこから人に移って咬みつくという事もありえますので、散歩から帰ったら、ブラッシング必須です。
特に毛足の長いスタイルにしている子は、持ち帰りやすいのでお腹周りや口周り、足回りをよくブラッシングしましょう。
マダニがよくつく体の部位
マダニが付きやすい体の部位は、皮膚の柔らかい場所が多いです。
目の周り、唇周り、耳、脇、股周り等が多いように思います。
毛が密集しているので探すのは大変ですが、ポイントを絞ってチェックをすると良いと思います。
また、ドライヤーの風を皮膚に当てるとチェックしやすくなるので、試してみて下さい。
「マダニは、シャンプーすればOKでしょ」は、間違い!
マダニは、シャンプーしても駆除できません。
濡れている時は、一時的に仮死状態になって動きが鈍くなりますが、乾くと同時にマダニも復活します。
マダニに水攻めは、効果は無いのです。
では、マダニを見つけてしまったら、どのように対処したら良いのでしょうか?
マダニを見つけてしまったら・・・
まず、潰すのはNGです。
一説によると、卵を持ったマダニを潰してしまうと、卵が飛び出してしまうからと言われています。
では、どうするのか。
- 病院で取ってもらう。
- 潰さずに、ガムテープに貼り付ける。
- 濃度の濃いハイターにつける。 一晩放置。
普通の虫なら、シャンプー剤や洗剤につけるとすぐに天に召されていきますが、マダニはそうはいきません。
なんなら、ハイター水の中でしばらく泳いだりしています。
一晩放置すると、ようやく完全に体が溶けてなくなります。
ほんとは怖い、ダニ媒介感染症
「ダニ媒介感染症」とは、病原体を保有するダニに咬まれる事で起こる感染症の事です。
公園などの草むらに生息しているマダニが人に咬みつき、病気を発生させるのです。
近年ニュースでよく取り上げられているのが、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」です。
SFTSウィルスを保有するマダニに咬まれる事により感染し、潜伏期間は6~14日と言われています。
症状は、発熱、消化器症状(嘔吐、下痢、腹痛、下血)が主で、腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ筋腫脹、出血症状を伴う事もあります。
また、血小板減少、白血球減少、血清酵素の上昇も認められるそうです。
致死率10%~30%。
万が一、マダニに咬まれてしまったら、早急に病院に行って取ってもらいましょう。
強引につまんでしまうとダニの体の一部が皮膚に残ってしまいますので、病院で取ってもらう事をお勧めします。
マダニの一生(寿命:1~3年程度)
犬の体についた卵から孵化
↓
幼ダニ 体調1mm(4~5日吸血後に地上に落下。1週間程で脱皮して、若ダニに成長し犬の体へ。)
↓
若ダニ 体調1.6mm(7~10日間の吸血後に地上へ落下。脱皮して成ダニになり犬の体へ。)
↓
成ダニ 体調3mm以上(2週間以上かけて吸血後に地上へ落下。)
↓
産卵
↓
1か月以内に、最大3000個の卵を産卵
※ 成ダニは吸血後はブドウ程の大きさになる時もあり、イボかと勘違いする程の大きさになります。
正直トラウマレベルで気持ち悪いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
愛犬家なら春先は蚤ダニの投薬やら狂犬病ワクチンやらで何かと出費が重なる時期ですが、リスクを考えるといたしかたないですよね。
厄介者のマダニですが、唯一救いがあるとするなら、マダニは動きが非常にゆっくりです。
蚤のように、ピンッと飛び跳ねたりもしません。
万が一見つけてしまっても、慌てず落ち着いて対処しましょう。
ではでは。Bye(*・ω・)ノ
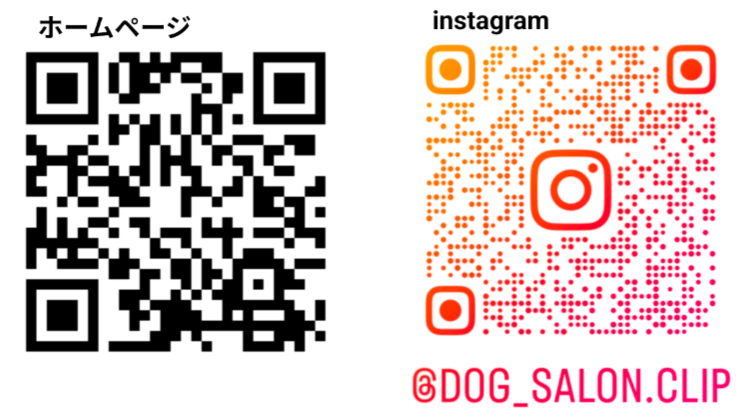
- 当ブログは、プロモーションを含みます。
- 当ブログの情報で不利益があっても、当ブログでは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
- 当ブログで紹介した商品の購入は、自己責任でお願いいたします。
- 当ブログの内容はできる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保障するものではありません。情報が古くなっている事もございます。
- 意図せず著作権や肖像権を侵害してしまった場合は、速やかに対処致します。
- 当ブログ内の文章や画像を無断で転載する事を禁止します。



